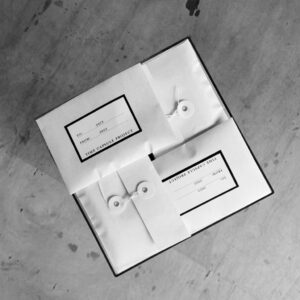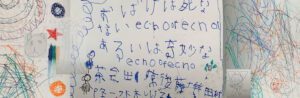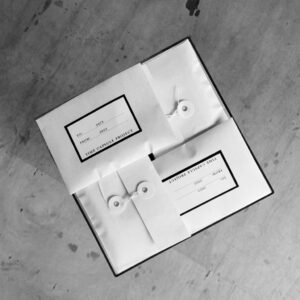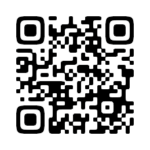ステートメント
生きられた家で、耳を澄ます

この家は、展覧会主催者である私の、友人のひいおばあちゃん夫妻が昭和12年に建てた日本家屋であり、今年で85年の歴史を持つ家だ。
親子代々に渡り一つの家に住み続ける、家を守る、家業のためではなく家を継ぐということはどういうことなのか、そのようなことが私にとって思考テーマのようなものになってしまった。私の両親は311の時に石巻で被災し、その後私が住む東京に移住した。が、一方で、被災しても留まり続け、再び家を建てる人もいる。それは、私から見ると、土地や家という概念を継いでいるように思えて仕方がない。
家を継いでいるような場所で覚えているのは、石巻にある母の親戚の家だ。同じ敷地に二つの店があり、店と店は台所兼居間で繋がっていた。その空間で大人数のご飯を作っていた光景が忘れられない。それぞれの店で働く女性たち、家事手伝いとして働いている親戚の女性たち、彼女たちは、いつも何かおかずを作っており、いつも私を歓迎し、私に食べるように勧めてくれた(多分、「とっちゃんも食べらいん」などと言われていたような気がする)。覚えている限りでは、家の食卓にはのぼらない三平汁、ずんだ餅などをご馳走になった。
そのような家の営みは地方だけのものであり、東京にはないだろうと思っていたが、友人がかつて住んでいた『この家』がまさにそうだった。一時期は、ひいおばあちゃん、おばあちゃん、お母さん、友人という、三世帯四代が住む家であった。先日、古い写真を見せていただく機会があったのだが、そこには、和室で家族や親族が集って食事を囲む様子が写っていた。その光景を見た時に、上述の石巻の親戚の家を思い出した。その写真と私の記憶から、女性が家を守り継いでいく歴史のようなものが頭に浮かんだ。
この家のことをアートプロデューサーの後藤繁雄さんに話したところ、多木浩二著作の「生きられた家 経験と象徴」を読むことを勧められた。本の冒頭の文章を以下に引用する。
どんな古く醜い家でも、人が住むかぎりは不思議な鼓動を失わないものである。変化しながら安定している、しかし、決して静止することのないあの自動修復回路のようなシステムである。磨滅したか風化してぼろぼろになった敷居や柱も、傷だらけの壁や天井のしみも、動いているそのシステムのなかでは時間のかたちに見えてくる。住むことが日々すべてを現在のなかにならべかえるからである。家はただの構築物ではなく、生きられる空間であり、生きられる時間である。
床をふく、畳をはく、障子をはたく、そのような日々のメンテナンスや、ご飯を炊く、野菜を切る、鍋に火をつける、器に盛る、というような日々の営みが、人が住む家の自動修復回路であり、家を長く生きたものにし、家の鼓動を絶やさないことに繋がるのだろう。
なるほど、『この家』が「生きられた家」だったのだ。この家では三代の女性たちが家を85年に渡り、生きられる家にしてきた。そして、生きられた家で幼少期を過ごした友人は家のパーツを再び生きられるものとして様々な方法で残そうとしている。その事態に遭遇した私は、生きられた家を別な形で、再び生きられる空間にしたいと思った。それがこの展覧会に繋がる。
展覧会に作品を出品したアーティストたちには、生きられた家で耳を澄まし、家の鼓動を聞いてほしいと思った。来場者にも作品から感じる鼓動と85年生きられた家の鼓動を聞き比べてほしい。そしてこの生きられた家の記憶を持つ方々にも、別な形ではあるものの、生きられる空間で新たな鼓動を聞いて欲しい。
なお、展覧会のアーティスト、スタッフは皆、後藤繁雄さんが主宰する、SUPERSCHOOL online A&Eの受講生である。また私は、銀座奥野ビル306号室プロジェクト(奥野ビルにあった元美容室の一室を維持する活動)に参加しており、306号室でもA&E受講生の展示を行ってきた。これまで、そして今回も、後藤さんにはいろいろなヒントをいただいた。今後も私は記憶が蓄積された部屋や家を追い続けていくだろう。生きられた家で耳を澄ます、ということを忘れずに活動を続けていきたい。
野村とし子(展覧会主催者)


PRIVATE HOUSE 生きられた家
コンテンポラリーアートのグループ展
築85年。練馬の日本家屋にて開催
© 2022 部屋と記憶 – Heya To Kioku –